おせち料理の基本の詰め方とは?食材の盛り付け方を紹介
こんにちは、イオン北海道eショップの三宮です。
色鮮やかなおせち料理は、目でも舌でも楽しめるお正月の楽しみの一つですね。
品数の多いおせち料理を重箱に詰めるには、ちょっとしたコツがあります。
ほんの少し気を付けるだけで、さらに美しく、よりおいしく見せることができますよ。
今回はおせち料理をきれいに詰めるコツや詰め方の種類をご紹介します。
由来や意味などのおせち料理の基本もお伝えするのでぜひ参考にしてくださいね。

※写真はイメージです。
おせち料理の基本とは?
おせち料理の「おせち」は漢字では「御節」と書きます。
「御節」とは季節の節目にあたる「節(せち)」のこと。
古来より日本では、季節の変わり目である1月1日の元日や、1月7日の七草の節句、3月3日の桃の節句などに、神様へ日ごろの感謝の気持ちを込めて、食べ物をお供えする風習がありました。
お供えのあとの食べ物は、神様のお下がりとしていただき、その恩恵にあずかると考えられています。
お供えする食べ物のことを「御節共(おせちく)」と呼び、これがおせち料理の語源とされています。
新たな一年を迎える元日は特にめでたい日とされ、現在では、正月に食べる料理を「おせち料理」と呼ぶようになりました。
神様をお迎えしている三が日の間は炊事をしないという風習から、日持ちのする料理を年末に作るようになったともいわれています。
おせち料理はその年の豊作と家族の安全を願うもの。
重箱に詰められているおせち料理一つひとつにもさまざまな願いが込められています。
諸説ありますが、主なものを3つご紹介します。
■数の子
ニシンの卵である数の子はとても数が多いことから子孫繁栄を願います。
■紅白かまぼこ
半円形のかまぼこの形は日の出に似ているため、おめでたい食材とされています。
また、赤は魔除け、白は清浄を表します。
■田作り
片口いわしの稚魚の飴炊き。
田んぼの肥料にいわしを使ったところ豊作になったことから、五穀豊穣を願います。
もっとたくさんのおせち料理の意味を知りたい方はぜひ「おせち料理とは?食べる意味や由来、食材の意味を知ろう」をご覧ください。
おせち料理の詰め方の種類やコツを紹介

※写真はイメージです。
おせち料理は重箱に詰めるのが一般的ですが、これには「福やめでたさを重ねる」という意味が込められています。
おせち料理の重箱の段数はさまざま。
五段重を正式とする説や四段重を正式とする説があります。
最近では、無理なく食べきれる量やコンパクトなサイズ感が好まれ、三段や二段のものも人気ですね。
おせち料理は「祝い肴」「口取り」「焼き物」「酢の物」「煮物」の大きく5つに分かれており、重箱のどの段に何を詰めるかが決まっています。
たとえば、四段の重箱に詰める場合は、次のように詰めるのが一般的です。
■一の重:祝い肴、口取り
祝い肴(いわいざかな)とは祝い膳として提供される酒の肴、口取りは口取り肴の略称で酒の肴を意味します。
田作り、黒豆、数の子、紅白かまぼこ など
■二の重:焼き物
焼き魚、エビ、はまぐり、肉巻き、ローストビーフ など
■三の重:煮物
里芋、レンコン、筑前煮 など
■四の重:酢の物
紅白なます、酢だこ、菊花かぶ など
おせち料理の詰め方の種類
一段に詰めるおせち料理の品数は奇数が基本。
偶数は2で割り切れるため、「割れる」や「分かれる」と捉えられ縁起が悪いとされています。
そのため、お正月のお祝いであるおせち料理の品数は3・5・7などの奇数です。
おせち料理の基本の詰め方をご紹介します。
おせち料理の品数を意識しながら詰め合わせていきましょう。
もちろん、基本の詰め方から自由にアレンジしてもOK。
詰める前に簡単なイラストを描いておくと、どこに何を詰めるかのイメージが掴みやすいですよ。
段取り
重箱を何段かに仕切って詰める方法です。
料理の詰めやすさや品数によって段数を増やしたり、減らしたりすることができます。
升かけ(ますかけ)
「手綱」と呼ばれることもある詰め方です。
重箱を斜めにまっすぐ仕切って詰めます。
区切る位置を変えれば、一列の幅を広く取れ、ボリュームのある食材を詰めることができます。
市松
正方形の重箱をさらに小さな正方形に分けて詰める方法。
初心者でも比較的簡単に詰めることができます。
品数の多い段におすすめです。
七宝詰め(しっぽうづめ)・隈取り(くまどり)
重箱の中央に1種類、その周囲を放射状に6種類、計7種類の料理を詰める七宝詰め。
四隅を仕切り4種類、中央の菱形に1種類の計5種類の料理を詰める場合は隅取りと呼ばれます。
中央に伊勢エビや鯛などを詰めると豪華で見栄えがします。
末広
重箱の中央に料理を置き、その他の料理を末広がりに配置します。
真ん中には小鉢を使うと詰めやすくなります。
末広はどこからでも「八の字」が見え、未来が大きく広がる「末広がり」で縁起が良いとされています。
きれいに盛り付ける詰め方のコツ
丁寧に詰めたおせち料理には、ちょっと意識するだけで、さらに美しく詰められるコツがあります。
ぜひ参考にしてください。
コツ①色合いを意識する
おせち料理を詰めるときは同じ系統の色が1カ所にかたまらないように、色のバランスに気をつけましょう。
色鮮やかなおせち料理ですが、例えば伊達巻きや栗きんとんなど同系色の食材が隣り合っていると地味な印象に。
その間に、紅白かまぼこや飾り葉を入れるなどして色を足し、全体の色のバランスも確認しましょう。
コツ②立体感を意識する
紅白かまぼこや伊達巻き、昆布巻きなどは重箱の端から立てて詰め、高さを出しましょう。
さらに重箱の真ん中が少し高くなるように盛り付けると立体感が出て、バランス良く見えます。
コツ③汁気のある料理にはカップを活用する
汁気のある酢の物や黒豆はカップを活用しましょう。
汁が重箱の中で広がってしまうことなく、食べ始めてからもきれいに保ちやすいです。
コツ④すき間を作らないようにして詰める
おせちは、すき間ができないようにしてキチッと詰めると豪華に見えます。
すき間ができないようにするには、奥から手前に向かって順に詰めていくのがポイント。
形がしっかりしたものから詰めていくときれいに仕上がります。
おせち料理をさらにグレードアップさせるには?
おせち料理の見栄えをさらに豪華にするには「あしらい」を使うのがおすすめ。
「あしらい」とは料理に敷いたり載せたりする飾りのことです。
「あしらい」を加えることでさらに彩りが加わり、見た目がワンランクアップしますよ。
おせちの盛り付けに慣れていない方でも簡単に取り入れられる方法なので、ぜひ、試してみてください。
「あしらい」には次のようなものがあります。
松の葉
松の葉は、針のように細い葉が特徴的です。
「長寿」の象徴として知られる松。
「松竹梅」の中の一つであることからも縁起が良いとされており、あしらいとして使われることの多い葉です。
はらん
はらんの葉は、大きな笹型で暗い緑色で光沢があります。
抗菌作用のある「はらん」は大きく丈夫なので、仕切りはもちろん、料理の下に敷くことも可能です。
味や匂い、色移りなどを防ぐ働きもするので、あしらいとしてとても重宝されます。
南天
南天とは、冬になると赤い実をつける木です。
「難」を転じて「福」にするという意味を持つ南天。
赤色は古くから魔除けの色ともいわれているため、おせち料理のあしらいにぴったりです。
お正月の時期になると100円ショップでも仕切りや飾り、祝い箸などさまざまなグッズが手に入ります。
100円ショップを利用すれば、リーズナブルにおせち料理をグッと華やかにできますよ。
おせち料理の詰め方の基本を知り、美しく盛り付けよう!
おせち料理は神様にお供えしていた食べ物「御節供(おせちく)」が由来。
おせち料理でその年の豊作と家族の安全を願います。
「福やめでたさを重ねる」という意味から重箱に詰めるのが一般的で、それぞれの重箱に入れる料理も決まっています。
重箱に詰める品数は奇数が基本。
詰め方にはいくつか種類があり、そこから自由にアレンジして構いません。
美しく盛り付けるには、色合いや立体感がポイント。
見た目をさらにグレードアップさせるために、あしらいも活用しましょう。
松の葉やはらん、南天などは縁起も良いとされているのでおせち料理にはぴったりです。
ほんの少しのコツを知っていればおせち料理はさらに美しく見えます。
どれも取り入れやすいものばかりなので、ぜひ試してくださいね。






















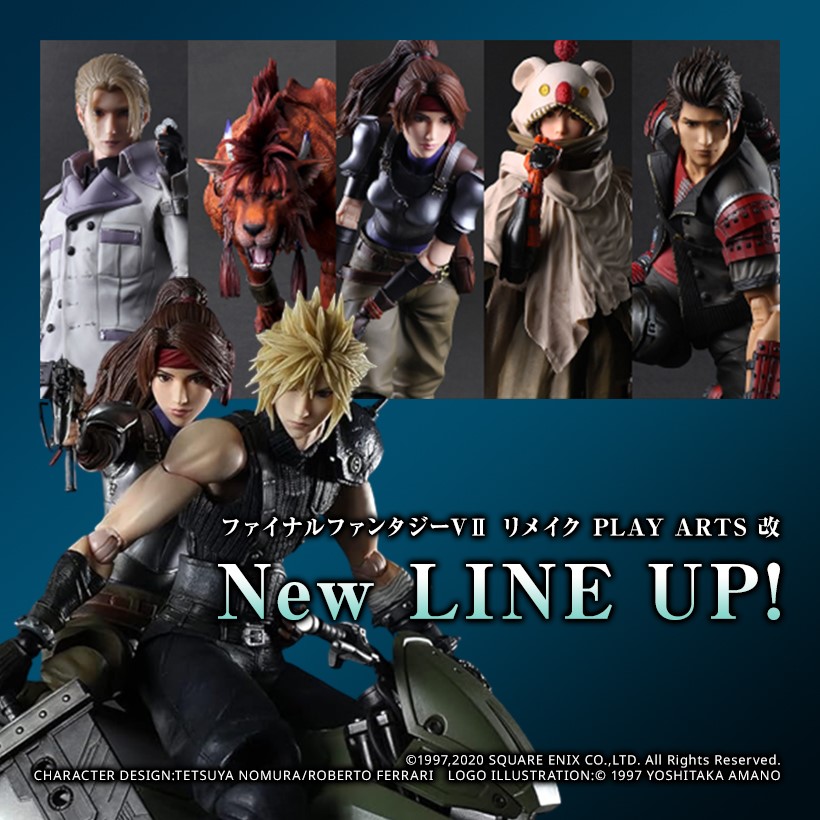











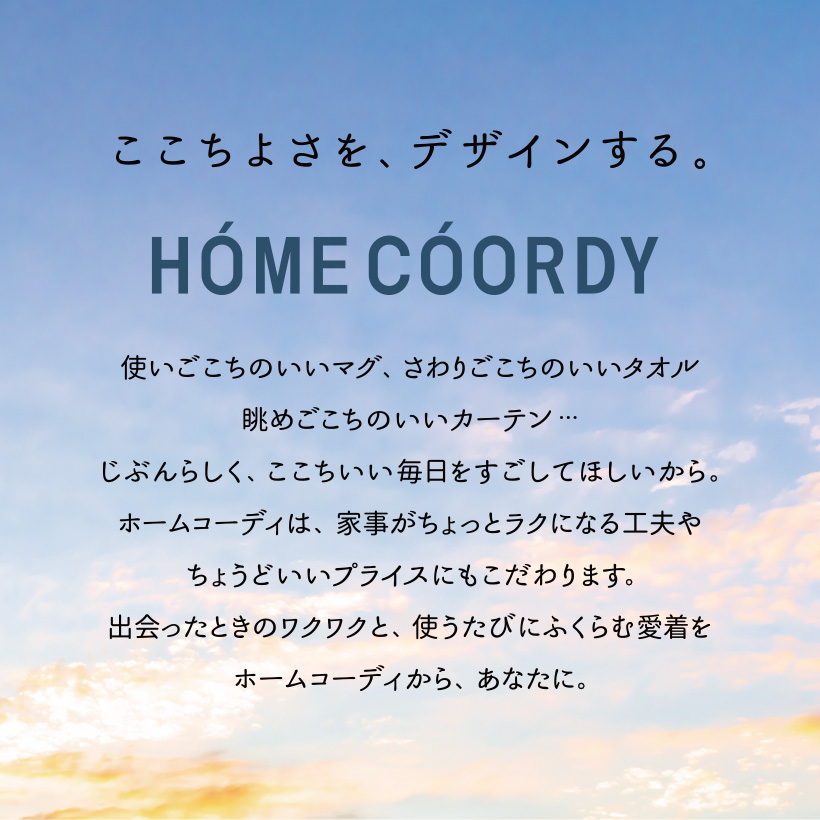

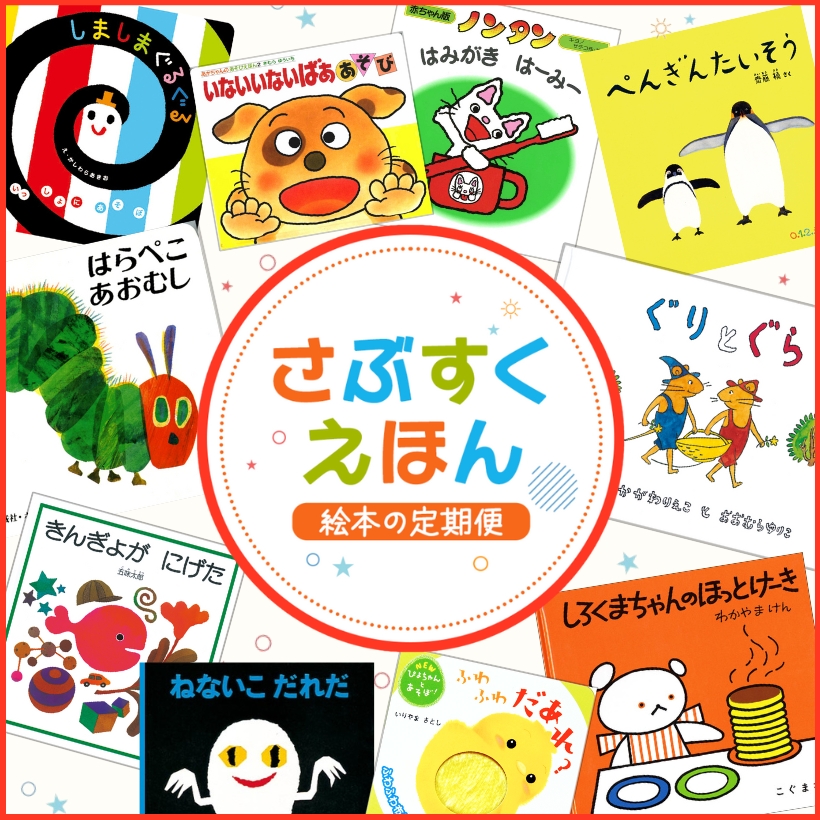

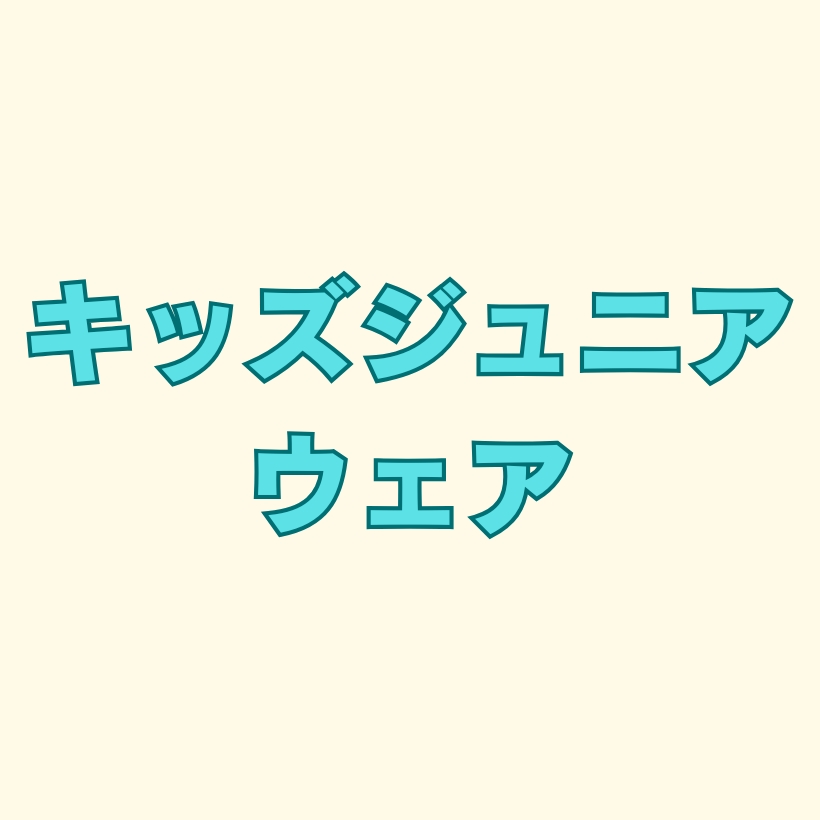







.png)












































