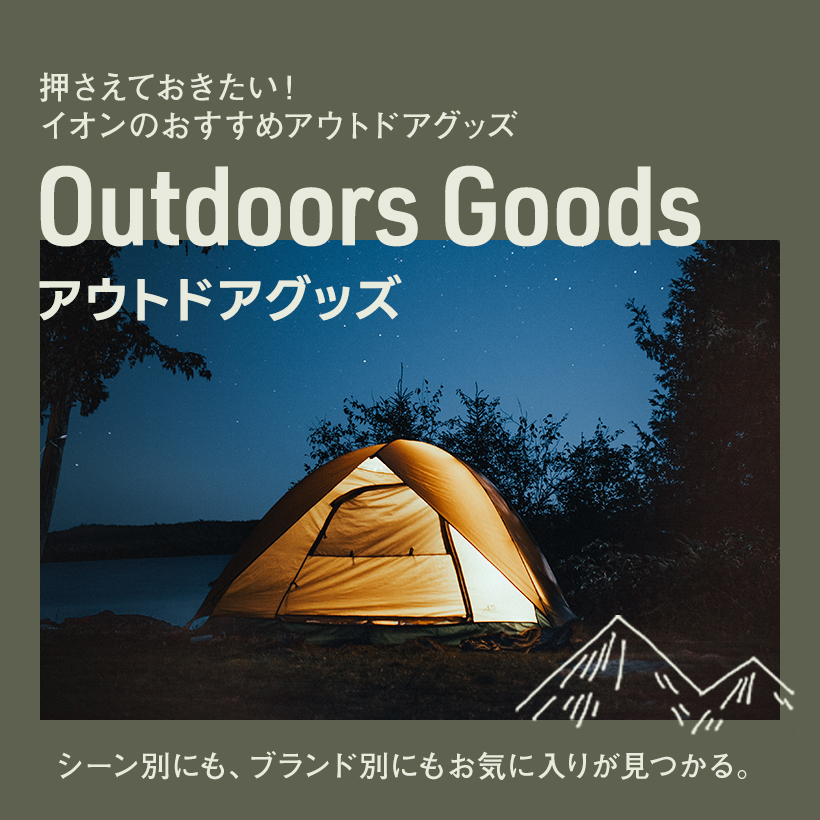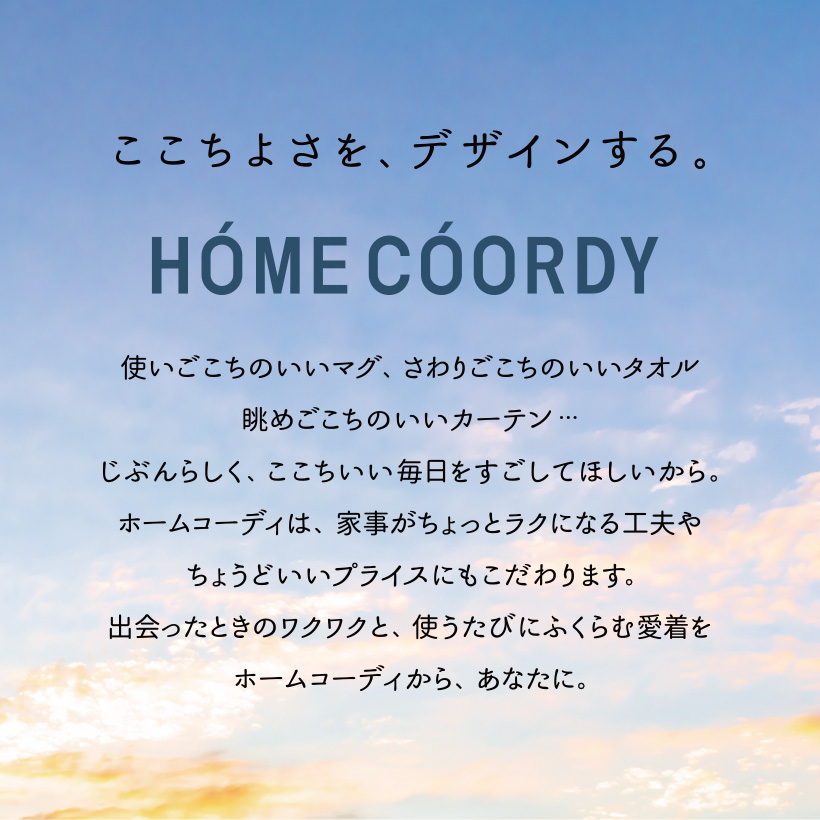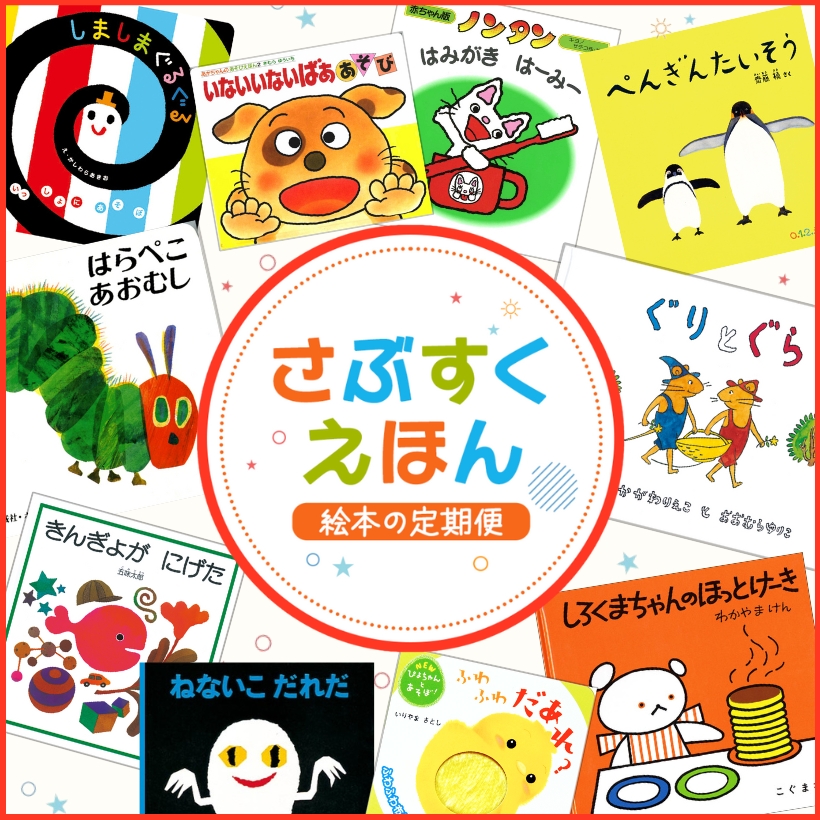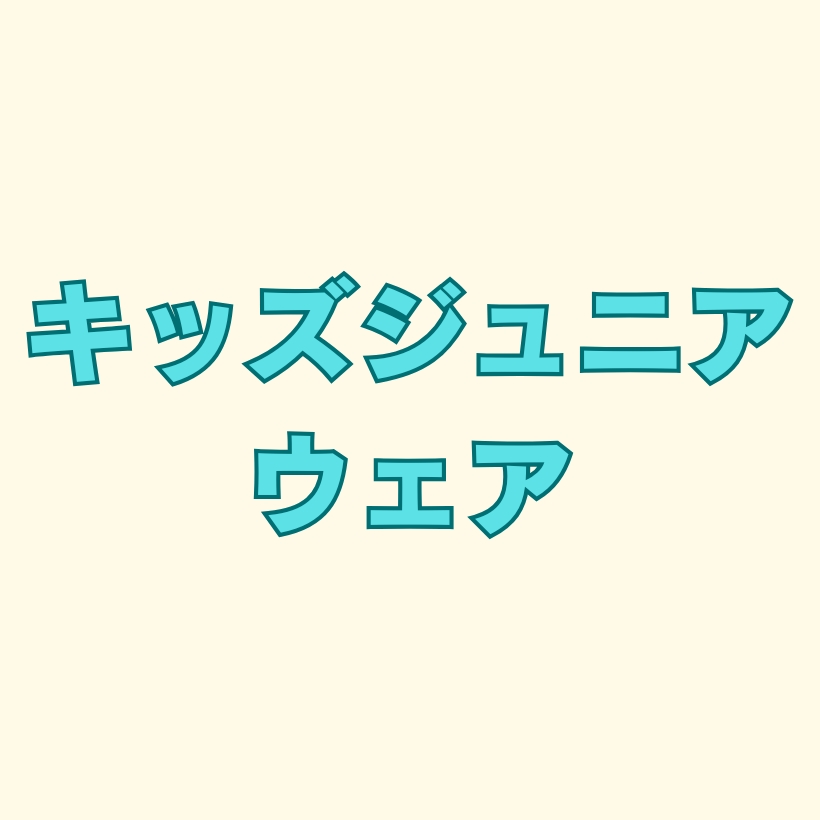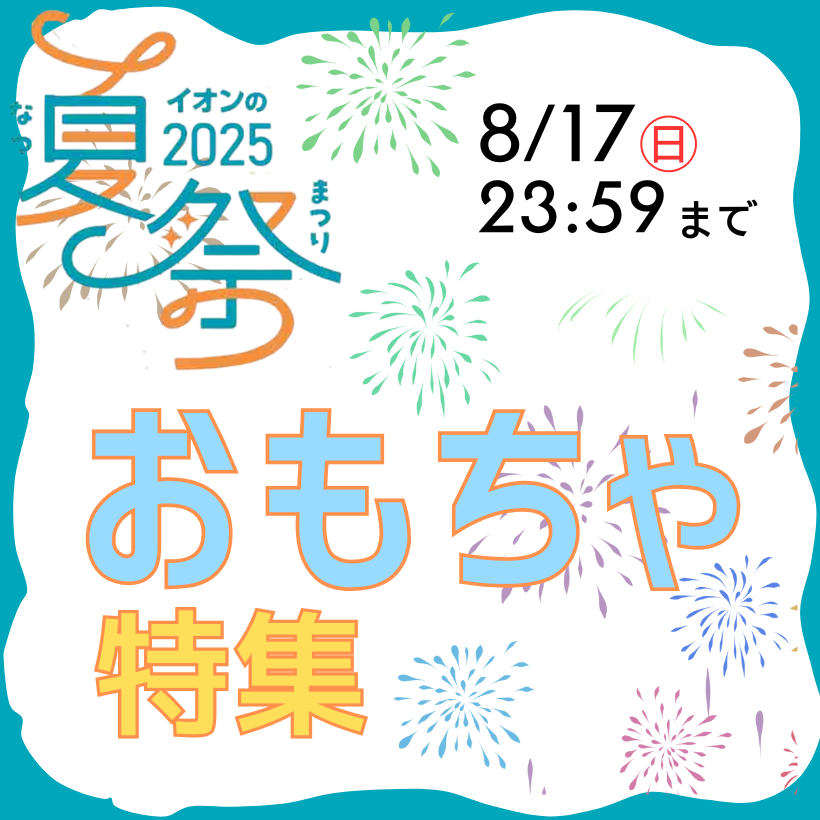おせちは北海道では大晦日に食べる!北海道ならではの風習
北海道には他の地域にはない独特の風習がいくつもあります。
お正月のおせち料理を大晦日から食べ始めることもそのひとつ。
今回は「北海道ならではのおせち料理の風習」についてのお話です。
北海道と本州で異なるおせちの風習をご紹介します。
北海道道民の方もそうでない方も、ぜひ読んでみてくださいね!

※写真はイメージです。
北海道のおせちは大晦日に食べる!どうしてそんな習慣に?
おせちと言えば1月1日の元旦に食べるお正月料理。しかし、北海道では大晦日の夜からおせち料理を食べ始める習わしがあります。
北海道以外でも東北地方の一部で同様に大晦日の夜からおせちを食べる習慣があるようです。
大晦日の夜からおせちを食べるという北海道の習慣は「年取り膳」という風習が元になっています。
年取り膳の意味は2つの説があります。
・新しい年を迎えるために大晦日から食べる料理
・旧暦では日没から1日が始まるため、旧暦では12月31日の夜から新年だった。新しい年が始まったのを祝って12月31日の夜に食べる料理。
いずれにしても北海道ではこの年取り膳の風習が残り、大晦日におせちを食べていると言われています。
おせち料理やお正月料理には北海道ならではの風習のものも!
おせち料理のメニューや素材などにも北海道独特のものがあります。・昆布巻きの中身は鮭ではなくニシン
・なますには氷頭(ひず)という鮭の軟骨の酢漬けが入っている
・煮物は「煮しめ」ではなく「うま煮」(煮物であることには変わりませんが…)
・茶碗蒸しは甘く、中には銀杏ではなく栗が入っている
このほかおせち料理の後、お正月にいただく「口取り菓子」もそのひとつ。
口取り菓子とは、鯛やエビ、松竹梅などのお正月の縁起物をかたどった和菓子です。
おせち料理に詰めたり、お正月料理と一緒にテーブルに並べたりしてお正月にいただきます。
北海道は土地柄から鯛やエビなどの食材が手に入らなかったことも多く、
その代わりにお菓子で表現をしておせち料理を作ったと言われています。
カラフルで可愛らしくおめでたい気分になりますし、甘い和菓子を食べて幸せな新年の始まりになりますね!
北海道は広いので、
同じ北海道でもエリアによって、おせち料理や正月にいただく料理の習わしがガラッと異なることもあります。
地元とは別の土地で年越しをすると新たな発見があるかもしれませんね。
北海道のおせちは大晦日、では正月は?

※写真はイメージです。
北海道ではお正月の元旦よりも、大晦日の夕食のほうが豪華になる傾向があります。親戚一同が集まっておせち料理をはじめ、刺し身やカニなどの海鮮グルメなどもテーブルに並び、
新しい年を迎えることをみんなで祝います。
昼間や夜食に年越しそばも食べますね。
年が明けてお正月にはおせち料理の残りやお雑煮、煮物などを食べます。
新年に食べる分のおせちをあらかじめよけておく、なんて家庭もあるようです。
先ほどお話した「口取り菓子」をいただく家庭もあります。
また、親戚やお客様がいる場合はお寿司の出前をとってもてなすという地域も多いです。
まとめ
・北海道では大晦日におせち料理を食べる風習があります。大晦日に食べて新年を迎える料理「年取り膳」の風習が残ったものと言われています。
・おせち料理のメニューや素材、お正月料理にも北海道独自のものがたくさん。
昆布巻きやなますの中身が独特だったり、煮物は「うま煮」と呼んだり、茶碗蒸しの中身は栗だったりと特徴があります。
・鯛やエビ、縁起物などをかたどった和菓子「口取り菓子」も、お正月に食べる北海道ならではのもの。
鯛やエビが手に入りにくい北海道でおせち料理を用意する工夫のひとつとして生まれました。
・北海道では元旦よりも大晦日の方が豪華!元旦にはお雑煮やおせちの残りを食べます。
来客がある場合はお寿司の出前を注文してもてなすという地域もあるようです。