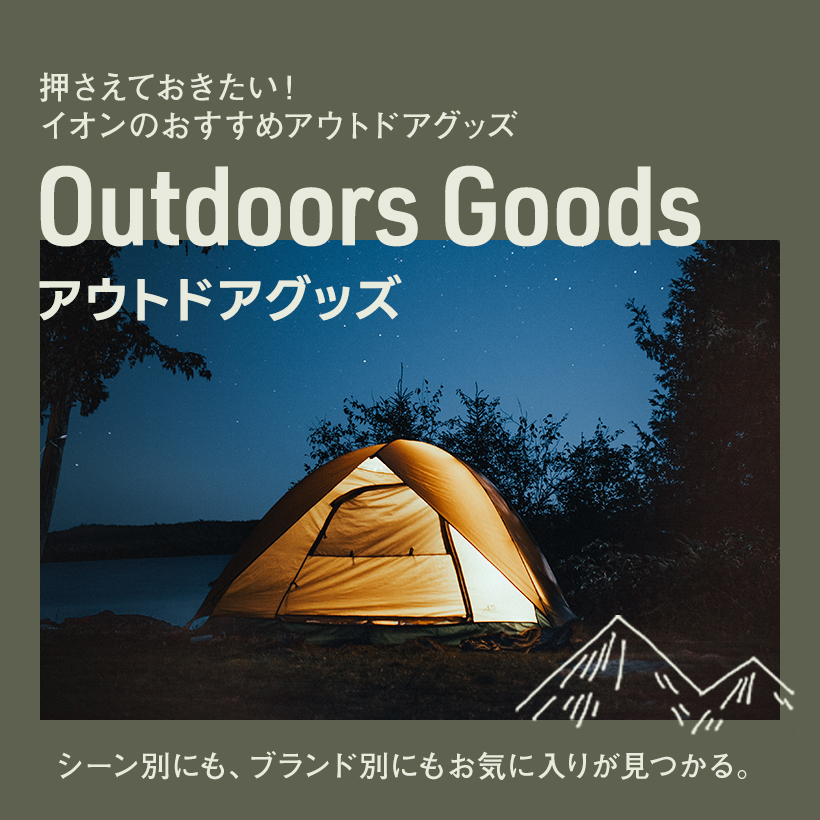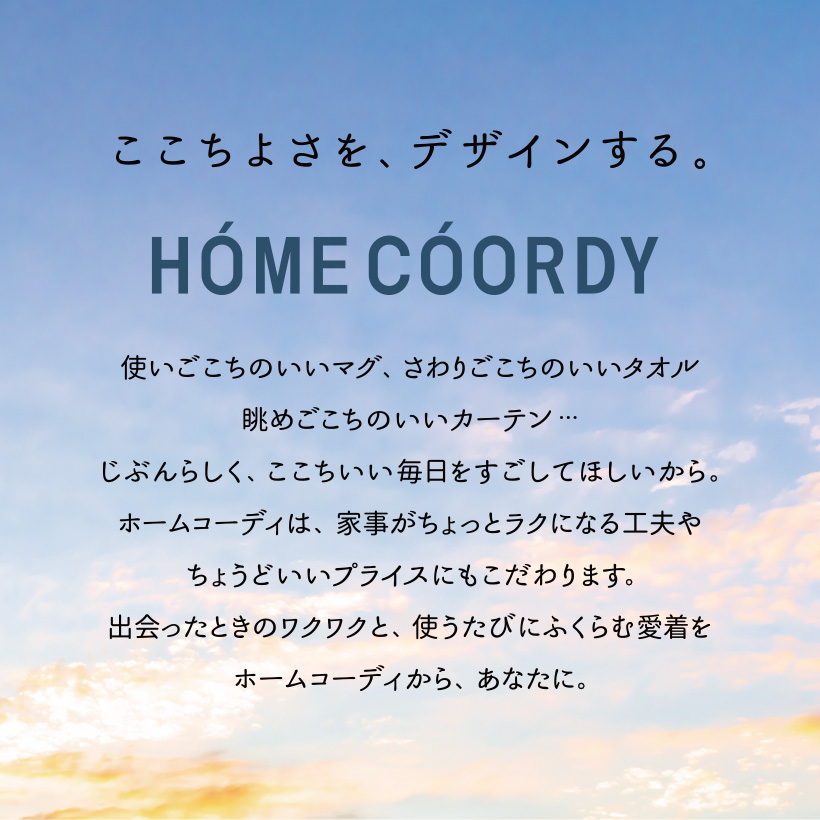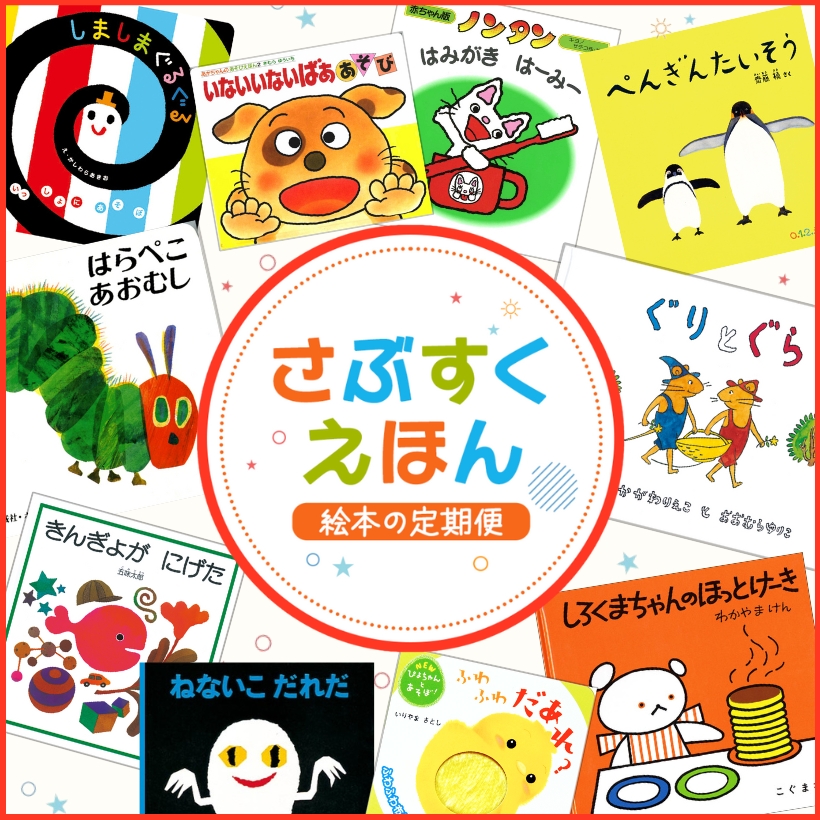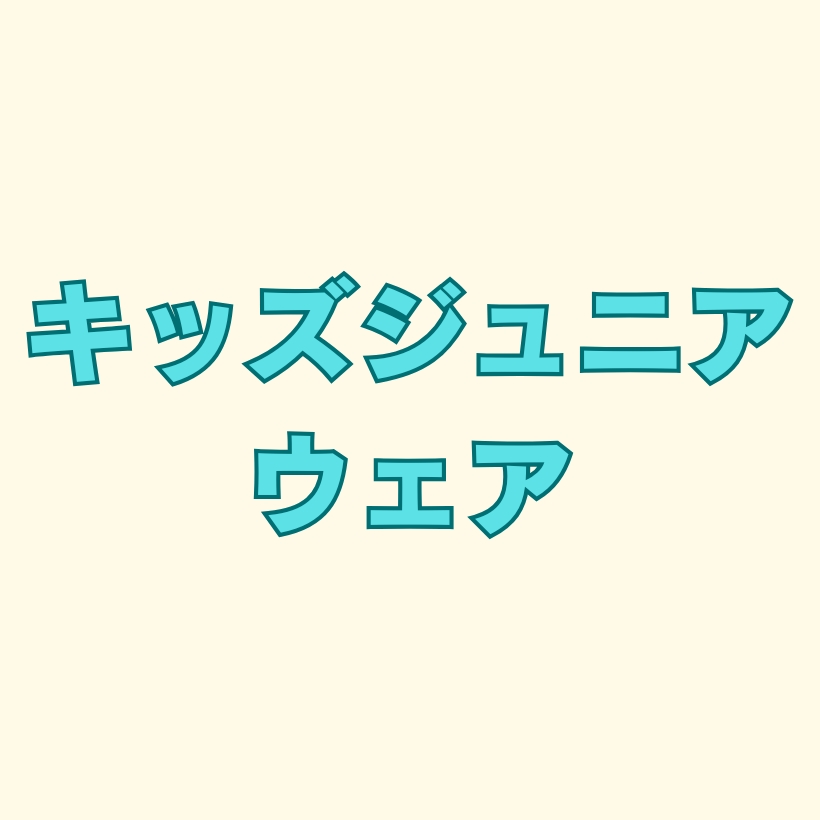北海道米が美味しくなった理由は?歴史・技術・魅力をご紹介
こんにちは、イオン北海道eショップの蒲です。
北海道といえば、美味しい食材の宝庫。
その中でも、近年ますます注目を集めているのが北海道米です。
今では「米の食味ランキング」で高評価を受けるブランド米も登場しているほどですが、実は「北海道米はあまり美味しくない…」といわれていた時代もあるんです。
では、なぜ北海道米はここまで美味しくなったのでしょうか?
その理由を歴史や技術の進化、そして品種ごとの魅力とともにご紹介します!

※写真はイメージです。
北海道米の歴史から美味しくなった理由を知ろう
北海道は寒さが厳しく、もともと稲作には適していない土地とされていました。
実際に、江戸時代に北海道で稲作が試みられたものの、厳しい寒さのためうまくいきませんでした。
その後、明治時代に本格的な開拓が進みましたが、北海道の気候は稲の生育に不向きで、長い間「美味しくない」「やっかいどう米」などと呼ばれていたこともありました。
転機となったのは、1873年(明治6年)のことです。
「北海道稲作の父」と呼ばれる中山久蔵が、「赤毛」という品種を用いて米作りに成功。
これをきっかけに、北海道各地へとお米作りが広まっていきました。
その後も研究者や農家が試行錯誤を重ね、寒さに強い品種の開発に取り組みました。
1980年には、北海道庁が「良質米の早期開発」プロジェクトを開始。
その成果として1988年に登場したのが「きらら397」です。
これにより北海道米の評価は一変し、全国の平均レベルに達するようになりました。
そして、さらなる品種改良が進み、「ななつぼし」や「ふっくりんこ」、北海道ブランド米の代表格「ゆめぴりか」が誕生しました。
特に「ゆめぴりか」は全国のブランド米と肩を並べるほどの人気を誇り、北海道米の地位を大きく向上させたのです。
北海道米が美味しくなった理由は「栽培技術」にある?
北海道米の美味しさは品種改良だけではありません。
栽培技術や収穫後の管理技術の進化も大きく貢献しています。
北海道の気候に対応するために発展した栽培技術
1990年代には、窒素肥料の使用を抑えることで、適度な粘りと柔らかさを持つ美味しいお米を育てる技術が確立されました。
しかし、肥料を抑えることで収穫量が減少するため、農家の方々はそのバランスを取りながら試行錯誤を重ね、高品質な米づくりを実現しました。
また、北海道では稲作を行うための気候条件が厳しく、北海道だからこその工夫が求められてきました。
雪が解け切る前からビニールハウスを準備して苗づくりを開始し、土を温めて籾まき後の発芽を促進する技術を取り入れるなど、先人たちの努力が今の美味しい北海道米につながっています。
北海道米をさらに美味しくする収穫後の技術
収穫後の品質管理技術の向上も北海道米の美味しさを支えています。
「超低温貯蔵」は、北海道の寒冷な気候を生かし、冬の冷たい空気を利用してお米を氷点下で保管する技術です。
超低温で籾のまま貯蔵することで、新米の品質を維持します。
この方法により、お米の劣化を防ぎ、長期間にわたって新米のような美味しさを保つことが可能となりました。
北海道米の美味しさを守る品質管理の徹底
品質管理の徹底も、北海道米の安定した美味しさの秘密です。
収穫されたお米は、色彩選別機などを用いて出荷前に徹底的な品質チェックを受けます。
厳格な基準に基づいた検査が行われ、基準を満たしたものだけが市場に流通する仕組みとなっています。
こうした品質管理の努力により、北海道米は全国でも高い評価を受けるブランド米へと成長しました。
北海道米(北海道ブランド米)の魅力とは?品種も確認

※写真はイメージです。
今や全国的に高い評価を得ている北海道米には、どのような魅力があるのでしょうか?
北海道米の特徴と魅力
北海道米の大きな特徴は、品種が豊富なことです。
広大な北海道では地域によって気候条件が異なるため、それぞれの地域に適した品種が栽培されています。
甘みの強いもの、もっちりとした食感のもの、あっさりとした味わいのものなど、好みに合わせて選べるバリエーションの豊かさが魅力です。
また、北海道は夏でも比較的涼しく湿度が低いため、病気や害虫が発生しにくい環境にあります。
そのため農薬や化学肥料の使用を抑えた栽培が可能で、安心・安全なお米づくりが行われています。
さらに、北海道の広大な土地を活かした大規模農業により、効率的な生産が実現。
この生産性の高さも北海道米の強みといえるでしょう。
代表的な北海道米の品種
北海道には多くの品種のお米がありますが、中でも人気が高い3つの品種をご紹介します!
ゆめぴりか
北海道米の最上級ブランドとされる「ゆめぴりか」。
全国食味ランキングで特Aランクを連続して受賞しており、北海道米の中でも特に人気の高い品種です。
甘みが強く濃い味わいが特徴で、北海道米の中でも粘りが強く、ツヤっとした美しい炊き上がり。
シンプルに白いごはんそのものを味わうのもおすすめです。
ななつぼし
「北斗七星のように輝いてほしい」という願いを込めて付けられた「ななつぼし」。
甘みと粘りのバランスが良く、特に冷めても美味しさが持続するため、お弁当やおにぎりに向いています。
さっぱりとした味わいで、酢飯にも相性が良いのが特徴です。
北海道内での作付面積第1位を誇り、道内で最も多く食べられている品種です。
ふっくりんこ
「ふっくりんこ」は、その名前の通りふっくらとした食感が特徴の品種です。
道南地域で開発され、和食やお魚料理との相性が抜群。
豊かな甘みとほどよい硬さがあり、飲食店やホテルなどでも採用される、プロにも支持される品種です。
この他にも、粘りが強く冷めても甘みのある「おぼろづき」、粘り気と柔らかさのバランスが取れた「ほしのゆめ」、雪のように白く艶やかな「ゆきさやか」など、個性豊かな品種が北海道各地で栽培されています。
「北海道のお米のブランドをご紹介!その美味しさの魅力や特徴を詳しく」では、人気の北海道米のブランドをさらにご紹介しています。
北海道米が美味しくなった理由には先人たちの努力があった!
かつては「美味しくない」と言われていたこともある北海道米ですが、長年の品種改良と技術の進化によって飛躍的に美味しくなりました。
寒冷地に適した品種の開発や、厳しい気候に対応する栽培技術、さらに収穫後の品質管理の徹底が、その美味しさを支えています。
特に「ゆめぴりか」や「ななつぼし」などのブランド米は全国的にも高評価を受け、北海道米の存在感を高めています。
品種が豊富で料理や好みに合わせて選ぶことができるのも北海道米の魅力の一つ。
ぜひ、お気に入りの品種を見つけて、その味わいを堪能してくださいね。